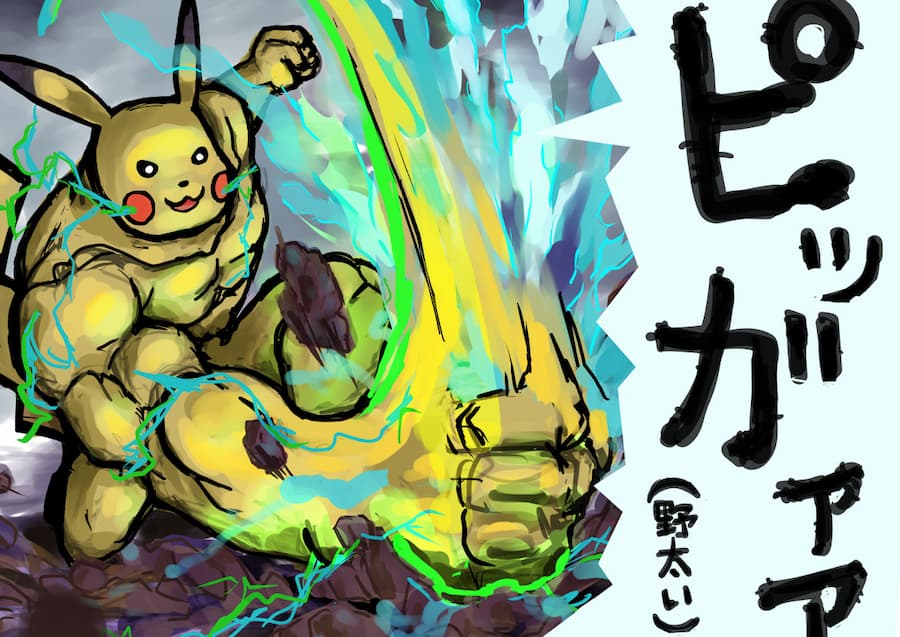「絵師として、XなどのSNSで知名度を上げていくために、二次創作の力も借りましょう!」というのは、沢山の著名な方々も仰っていることだと思います。絵、イラストの世界で、一次創作だけで知名度を上げるのがとても難しいことは、誰でも感じていることでしょう。
「二次創作は似てないとダメ」の意味を考える
皆さんはこの言葉を聞いたとき、どう思いましたか?この言葉の前後の文脈が大事なのはもちろんなのですが、まぁまずは注目を引いて、興味を持ってもらうのが第一なので、色々なところで強めの言葉が使われがちなわけです。絵のことに限った話じゃないですけど、サムネで不安や反発を煽って、クリックしてほしいわけですね。「〇〇の場合なら似てないとダメ」みたいな前置きがあったとしても、「じゃないとダメ」という言葉が強いので、そこだけ一人歩きしやすい表現だと思います。若い人や純粋な人ほど影響されやすいので、相手のことを考えて何かを教えるなら、気を付けたいところです。私はこういうキツめの断定口調はなるべく使わないようにしています。
私自身は結構、描く人の絵柄の個性が出ている二次創作、ファンアートが好きなのですが、「原作に似てないとダメ」と考えている人は多いと思います。その理由として、
- 原作の絵柄に似せてないのは原作に対するリスペクトがない
- 自分の個性が出したいなら一次創作だけしていろ、二次創作を売名の道具にするな
- 原作に似ていない二次創作なんて見たくない
やや過激な文言になってしまったかもしれませんが、率直に表すとこの3つが大体の理由でしょうか。
まず1については、ただの言いがかりに近いものだと思います。リスペクトのあるなしが、原作に似ているかどうかと、どのような関係があるのか、「絵柄を似せることはリスペクトの一つ」というのは理解できても、だからといって「似せていないということはリスペクトしていないということ」となる理屈が極端すぎて、よく分からないのです。好きなものを好きなように描いてネットにあげること自体が、非難されるようなことではないはずだし、こんなこと言うやつがいるのかという感じですが、聞いたことがある気もするし極端な人も多いので、まぁ一応理由の一つに入れました。でもこれ、同じじゃないとダメだろ、同じじゃなくてもいいだろ、とそれぞれが思うのは好みの問題なので、自由だと思います。排斥がよくないということですね。
2についてもやはり、自分の絵の個性を混ぜた二次創作をしたっていいじゃないかで済んでしまう話です。ただ、「売名の道具にするな」に関しては、二次創作というものが基本的に、それで金銭を稼ぐことをよしとしないため、知名度を上げるという「得をする行為」も許せないのだと思います。知名度の高さがマネタイズに繋がることが否めないからですね。じゃあ実際にどの程度までが、「二次創作でお金を稼ぐ行為」に該当するのか考え出すと、境界が曖昧過ぎて難しいです。
「描いた絵を直接売る」のはあまり許されていない風潮を感じますね。しかしもちろんやってらっしゃる方は居ますし、度を越した悪質なものでなければ、権利者もわざわざ時間を使って警告するほどではないようです。二次創作の同人活動なども、あまり儲けを出さない値段設定にするなどの暗黙の了解が存在する感じです。
「描いた絵のメイキング動画や、絵を描くノウハウの解説に使われる程度」などは割と許されている空気を感じますね。これは著名な方々もユーチューブ動画などにして、やってらっしゃるイメージです。
まぁ私の個人的な印象の話をしていますし、引用の範囲が云々だとか、どこまでが大丈夫なのか、ここでそういう話をするつもりも知識もありません。「自分が好きなもので、権利者以外の人間があらゆる得をすることを許さない」という理屈に関してはまぁ、いわゆる「嫌儲」思想が過ぎるとは思いつつも、気持ちが理解できなくもないという感じでしょうか。しかしそれを罰する権利があるのは権利者だけということも覚えておかないといけません。界隈が二次創作で盛り上がることは、いい点も悪い点もあるという事実が存在するのみです。
3に関しては完全に好みの問題なので、自由でしょう。「俺の視界に入れたくないから描くな」までいくと、おかしな話になると思います。
二次創作は似ないとウケないのか
上のお気持ち表明みたいなのよりは、こっちの文章の方が役には立つかもしれません。
で、この似てないとウケないのかっていうのは、ぶっちゃけ、その傾向がかなり強いでしょう。絵を描く人、上手な人が他人の絵を見るときは、結構その人の絵柄の個性も、良い味として受け取ってくれることが多い気がするのですが、普段自分で絵を描かない人、ただ原作が好きな人にとっては、「似ていること、同じであること」が「いい絵であること」とイコールになりやすいと思うのです。それに加えてもう一つの、絵を描かない人に好印象を抱かせるのに効果てきめんな要素が、「写真かと思うほど精巧で綺麗」と「写真のようなピント合わせ」です。「そっくりに描いてあること」以外に、絵の評価基準をあまり持っていないことが多いからではないでしょうか。もちろんこれは馬鹿にしているわけではなく、分析して考えたらこうかな?ということです。
現実の物体と見分けがつかないようなデッサン、着色がしてある絵のメイキング動画とかがウケるのも、その技量が凄いのと同時に「同じで凄い!」が分かりやすいからでしょう。なので、「原作と同じ絵柄で、背景や小物、服などの質感が写真かと思うほど綺麗で、キャラの背景や前景の物体などが必要に応じて、カメラで写したように適度にボケたりしている」、これが最強だと思います。他には、「不気味の谷を越えるほどの顔のリアル化」や「SDキャラ化」なども分かりやすい上手さですね。ここにさらに、公式の絵ではあまり見られないようなシーンやアイデアを盛りましょう。
でも正直、写真と同じ、原作と同じだけじゃなくて、そこに線の強弱や色のコントラストなどを使って、目立たせたい要素を強めたり描きこんだり、不要な要素を弱めたり省略したり、キャラも背景もデフォルメの加減とか、そういう部分に自分なりに試行錯誤することも、大きな「絵の上手さ」の基準の一つだと思うのです。自分の絵柄の個性を、違和感が出ない程度を探りながら混ぜたりとかも、上手さの一つです。悲しいかな、このあたりはあまり目立たない上手さであることも多いので残念ですが……
原作絵に似てなくても許容されそうなジャンル
例えば私がよく描いているドラゴンクエストやファイナルファンタジーのファンアートは、見る側も結構、いろいろな絵柄に寛容な気がするし、割と様々な画風のファンアートが流れてきて、いいねとかも多かったりします。何故なのか自分なりに考えてみました。
まずドラクエについては、元々の鳥山先生の絵柄に加えて、小説の絵を担当したいのまた先生たちや、4コマ漫画劇場の様々な作家さん、ドットのグラフィックなど、色々な絵柄で表現されてきたというのが、幅広い画風が受け入れられやすい理由の一つかなと思いました。
ファイナルファンタジーに関してもゲームのドット絵、それより綺麗なムービーシーン、公式絵に加えて、天野先生の絵も印象が強く、こちらも様々な絵柄で表現されていたりします。スピンオフ作品の多さからくる画風の微妙な違いも影響しているかもしれません。
また、両シリーズとも、見る側も描く側も平均年齢がおそらく高めで、そこも描く人の個性に寛容な理由かなと思いました。違うからダメ、になりにくく、それも楽しめる程度に成熟してきているのかなと。
似たような理由で、レトロなコンシューマゲームのファンアートは割と、懐かしさとか、そもそも絵の数の少なさなどから、描くと喜ばれることが多い気がします。
ゲームは結構みんないろいろな画風に優しい……と言いたいところなのですが、同じゲームでも、人気スマホゲームとかになると、原作と違う絵柄に厳しいイメージがあります。客層によるということですね。
あとは漫画やアニメも、絵柄が似ていることが、まずは反応が良くなるための第一条件という感じがします。私も、ドラクエの絵ならいろいろな画風で楽しんで見られるけど、鳥山先生ぽくない絵柄でドラゴンボールやDr.スランプのファンアートが流れてきたとして、すぐに楽しむことができるかどうかはわからないというのが正直なところです。
知名度を上げるための二次創作の難しさ
ここから、一次創作だけじゃなくて二次創作の力も借りよう、という言葉について考えます。
二次創作が似てないとウケないから似せて描く、それでXなどのSNSのアカウントが大きくなったとしましょう。
今度はそのアカウントで、自分の個性全開の絵柄で一次創作を見せたとして、いい反応に繋がると思いますか?私は、繋がらないと思います。特定の二次創作で集めたアカウントで突然一次創作のイラストを上げても、いいねやリポストは大体ガクーーーっと落ちます。いろいろな二次創作の絵の上手いアカウントを拝見しても、そうなっていることが多いです。描いていた二次創作に近い絵柄であれば落差はマシになるかもしれませんが、それでも下がるでしょう。アカウントを分けたとしたら、そもそも見に来る人が少ないと思います。ここが二次創作の力を知名度に変える難しさだと思うのです。
Aという原作の絵柄に似せて二次創作で知名度が上がっても、見る人は「Aの二次創作を描くあなた」としか認識しないでしょう。でも、知名度を上げた先に絵の仕事がしたいという理想があったとして、その二次創作の絵柄に似た絵を描いてほしいクライアントからの仕事は、来るかもしれません。あなたの描きたい絵も同じ画風である場合や、どんな形であれ絵でお金が稼げればいいというなら、それで問題ないと思います。
違う場合や、「最終的には自分が表現したいものを描きたい場合」は、評価されない一次創作を描くのが苦しくなってしまうかもしれません。
私は現状絵でお金を稼ごうとは思っていませんが、上に書いたことをどうすればいいかを考えた時の私なりの答えが、ある程度、自分の絵柄で二次創作を描くということなのです。いろいろな異なる種類の二次創作をたくさん描くとさらにいいです。どれだけ原作の画風に寄せるかは描く人次第で、このあたりの加減がセンスによるものかもしれませんが、どんな二次創作を描いても、あぁ、この人の絵だな、と認識してくれる人が多ければ多いほどいいです。その上でついたファンが多くなってくると、それは程度の差はあれど、あなたの絵柄が好きな人たちだと思うのです。いいねやリポストをくれるのが「あなたのファン」なのかということを考えると、また難しくなってくるのですが……フォロワーの増やし方について描いた記事もあるので、良かったら読んでください。
あるいは逆に振り切ってしまう手もあるかと思います。まずは「〇〇の二次創作のあなた」を極限まで高め、何らかの似た方向の仕事で実績を積んだ後の一次創作、ということです。肩書やブランドに弱い人が多いので、「あの〇〇のイラストレーターの一次創作か、やっぱり凄いな!」となるわけです。無名の一般人が描いた超上手いイラストよりも、有名人が描いたそこそこ上手いイラストの方が金銭的価値が生まれるのとも似ています。
一次創作だけじゃなかなか伸びないから二次創作も描いてみるか
こう思って、一次創作のアカウントで、特定の二次創作やファンアートを描いて載せだした方々は多いと思います。でも、上手くいきましたか?いつもの一次創作とあまり変わらない感じのいいね数だったりしませんでしたか?いいねとかリポストをくれるのは、大体がいつもの一次創作を上げた時と同じ人だったりとか。それだと二次創作が良かったからじゃなくて、あなたが描いたからいいねされたということだと思います。それはそれで嬉しいと思いますけども。
それほど規模が大きくないアカウントで、一次創作メインの人が唐突に載せた二次創作は、おっ、上手いなぁと思っても、原作に似ていないとあまり伸びていないことが多い気がします。伸びていることが多いと感じるのは、その後も継続して同じ二次創作を、絵柄を似せて定期的に描き続けるパターンです。一次創作のアカウントじゃなくて、もうその原作の二次創作アカウントやん……てなってる人も見たりします。二次創作をわかりやすく伸ばそうとするなら、場合によっては原作が好きなアカウントと交流する必要も出てきて、ますますアカウントの方向がブレます。似せろ!寄せろ!と言われる二次創作ですが、それを一次創作を描くための力にしようとすると、結局簡単にはいかなそうだなぁという話でした。